私には中度の自閉症と知的障害を併せ持つ兄がいます。
この記事では、兄が幼少期から大人になるまでに効果を感じた療育【TEACCHプログラム・音楽療法】を体験談を交えてお話しします。
同じように悩んでいるご家族や支援者の方のヒントになれば嬉しいです(^-^)
※昔は『自閉症』という診断名が一般的でしたが、現在では『自閉スペクトラム症(ASD)』と呼ばれることが多いです。この記事では、当時の表現として『自閉症』という言葉を使っています。
兄の成長記録
まずは、兄の経歴や母の行動などを簡単に紹介していきます(^-^)
誕生~1歳:運動発達の早さと母の気づき
1994年(平成6年)に誕生しました。2025年現在は、31歳です。
余談ですが、生まれた日はF1レーサーのセナ選手が亡くなった日なんです。
兄は、あまりにも運動面の成長が早かったので、父母は「セナ選手の生まれ変わりじゃないか!?」と思っていたそう(笑)
0歳の兄はよく泣き、よくミルクを飲む子でした。
しかし、母乳を飲みたがらず、市販のミルクを飲んでいました。
1歳では、走るほどにまで運動面が急成長していました。
抱っこを嫌がったりと、スキンシップを避ける様子はあるものの、自閉症と特徴といわれている目線が合わないなどは、この時みられませんでした。
また、本が大好きで図鑑や、絵本をよく見ていました。
母が毎日、読み聞かせをしており、兄はそれが楽しみだったようです。
1歳半検診では、特になにも指摘されることはありませんでしたが、母は言葉が遅いと思い、相談していたようです。
何かおかしいと、モヤモヤした母は、児童発達センターへ電話し、みてもらうことに。
診察すると、自閉傾向があるとハッキリそこで言われたそうです。
児童発達センターでの兄の様子はというと、先生と母が話している横で、回る椅子をくるくる回しながら、椅子に目線を合わせてじっと見ていたそうです。
私がこのエピソードを聞いた時、ドクターはやはり自閉の特徴について、理解されているんだなと思いました。
しかし、この時期(1995年~1996年)は、まだ『発達障害(自閉症)』の数は少なく、自閉症についての情報が少なかったので、母は不安でいっぱいになったそうです。
「そもそも自閉症ってなんだろう?」そう思った母は、いろいろな本を読んだり、自閉症の子を持つ方の講演会を聞きに行くなど情報収集を始めました。
その時代は、自閉症=重い精神病というイメージを持つ方も多かったようで、本には暗い印象のこともたくさん書いてあったそうです。
母は、本の内容が兄に当てはまらないことも多かったので、あまり鵜呑みにしていなかったそうなのですが、
どの本にも、講演会でも、『早期療育』という言葉が強調されており、母はまずは何か通ってみようと決意し、探し始めたそうです。
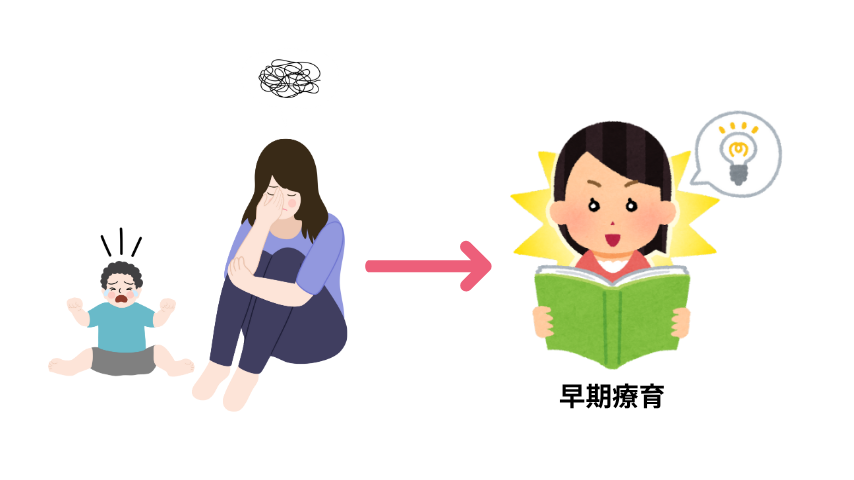
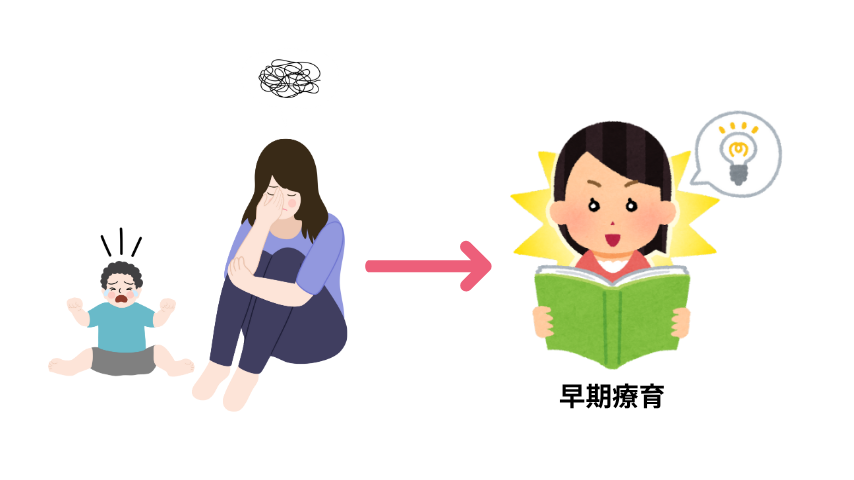
2歳半~3歳:診断と療育のスタート
2歳半に兄はついに病院で『自閉症+知的障害』の診断を受けました。
母はその診断をきっかけに、すぐに児童発達センターなどで療育(音楽療法など)を受けさせることを決めたそうです。
このころの兄は、多動傾向が強く、良く走り回る・飛び跳ねる、目を離したらすぐにどこかへ行ってしまう子だったそうです。
この多動傾向は小学校低学年まで続きましたが、中学年になってくると落ち着いてきました。
また、このころは、自閉症の特性といわれる『こだわり』が強くなってきたころでした。
・車のタイヤをチェックしたがる
・水を流したがる
・手すりの横を走りたがる
などなど。
また、『偏食』も目立ってきました。
この時の兄は、味噌煮込みうどん以外、食べなかったそうです。
偏食に関しては、経験を通して食べられるものが増えて、今ではいろいろなものを食べられるようになっています♪


4歳〜6歳:保育園と体操教室での経験
療育で音楽療法を続けていました。
楽器を鳴らすことなどはほとんどできず、音楽療法中は走り回ったり、落ち着かない様子だったようですが、
好きな音楽が流れたりすると笑顔をみせて、遠くから聴いていたり、お母さんと一緒にベルを鳴らしたり、太鼓をたたいたりと楽しむことができていました。
太鼓をたたいた時の振動が好きだったようで、鳴らした後に顔をぺったりと太鼓につけて感覚遊びをする様子もあったようです。
また、加配の先生をつけてもらいながら4歳から保育園へ通い始めました。
このころ発達障害の子が、保育園に通うパターンはあまりなかったため、加配の先生たちも戸惑っていたそうですが、とても勉強熱心な良い先生に恵まれて、兄はのびのびと過ごせていました。
私も、同じ保育園に通っていましたので、兄の様子を間近でみていましたが、いつもニコニコしていて本当に楽しそうでした。
兄の周りの子どもたちはというと、心無い言動を兄にする子もいましたが、守ってくれる子どもたちも、たくさんいたので、母は気にならなかったようです。
むしろ、兄が保育園でいろいろな経験をして、成長していく姿をみて感動していたそうです。
運動会やお祭りなど、集団行動や大きな音が苦手な兄は苦戦していたようですが、加配の先生が遠くからみるだけの日を作ったり、のんびりとした練習で少しずつ慣れさせてくれたおかげで、
本番は集団の中で鉄棒や踊りなどにチャレンジすることができたそうです!
素晴らしいですよね👏


また4歳からは、妹の私と一緒に、体操教室に通い始めました。
体操教室では、マット運動・平均台の上を走る・跳び箱・鉄棒・しっぽとりなどの身体遊びなどさまざまな運動を経験しました。
体操教室の先生(ハッピー先生)は、厳しい時もありましたが基本はのびのびと兄を見守ってくれる素敵な先生で、
他の子どもたちと混ざってできそうなところは一緒に行い、難しいところは兄のレベルに合わせてゆっくり取り組んでくださいました。
流す音楽などにこだわりがある兄は、自分が流してほしくない音楽が鳴った時に「いやー!」っと外へ脱走してしまうこともあったのですが(笑)
ハッピー先生が追いかけて、ギューッと抱き着いて気持ちを落ち着かせてくれたり、他の子が運動している時に好きなCDを聴かせて気持ちを落ち着かせてくれていました。
兄にすべて合わせることはせずに、あくまで兄が私たち(他の子どもたち)に混ざっておこなうことを考えてくれていました。
なので、兄だけが運動しない時間はほとんどなく、最後には絶対に兄が運動する時間を作って、他の子どもたちに見守られながら兄も頑張っていました。
思いっきり走っていても怒られない環境で発散できたのも兄にとってよかったようです。
そのかいもあってなのか、公園の遊具やキックボードなどの遊び、学校の体育の授業など、嫌がらずに取り組めました。
小学校の運動会のダンスなども上手に踊っていましたよ(^-^)


また、4・5歳では言語聴覚士によるティーチプログラムを受けて言葉をたくさん覚えることができたそうです。
ティーチプログラムは低学年まで続けていました。
覚える言葉が多くなったことで、こちらが言っている意味を理解して、動いてくれることが少し増えたそうです。
話すことは苦手で、4~6歳の頃は、「いや」・「くるま」など特定の単語のみ話すだけでした。


7歳〜12歳:小学校支援学級でのトラブルと成長
小学校は地元の特別支援学級へ通いました。
特別支援学級では相性が合わない先生もいて、心が不安定になることもあったそうです。
兄がトラウマになってしまったエピソードを少し話します。
偏食で食べられないものがまだ多くあった時期なのですが、自閉症の特性をあまり理解していない先生で、
無理やり食べさせられて、嘔吐してしまったり・・・
低学年の時は、大きな音がすると体育館に入れずパニックになってしまうこともまだあったのですが、
パニックになっている状態なのに無理やり腕を引っ張って連れていかれたり・・・
(強すぎて腕にあざができていました)
さまざまな出来事が重なって、学校に行き渋る様子があったり、自分の頭を叩くなどの自傷行為があったり、母に頑張って「痛い」などと単語で伝えようとしたり、不安定になっていました。
この時、母は学校に相談して解決策を考えてもらいながら、兄が学校に行きたくない時は休ませたりしていたそうです。
幸い、その先生以外に障害に理解ある素敵な先生もいて、その先生が担任になった時にはのびのび過ごすこともできていました。
それに小学校に入ったことで
- 本を読むことがもっと大好きになった
- 歌が歌えるようになった
- ひらがな、カタカナ、数字、簡単な漢字を読むことができるようになった
- 簡単な計算ができるようになった
- 言葉が2語文になった
- 人の顔の絵を描くことができるようになった
- 妹のピアノの発表会・花火を見に行くなど、嫌がりながらも挑戦して慣れることができた
- のりもの以外にも好きなものが増えた(Disney、プリキュア、ちびまるこちゃんなど)
このような成長がありました(^-^)
13歳〜18歳:中学・養護学校での新しい学び
中学校も特別支援学級のある、地元の中学校へ行きました。
中学校では、自由にさせてくれる先生で、小学校の時よりももっと、のびのびと過ごせていたようです。
中学生活で成長した部分は、
- 人の身体が描けるようになった
- バランスは悪いが文字や数字、漢字を書けるようになった
- 英語に興味を持つようになり、いくつか単語を覚えることができた
- 偏食が少なくなり、いろいろ食べられるようになった(よく食べるようになり太ってしまった)
- 言葉は3語文話せるようになった(まだ、本人の一方的な会話がほとんどで、質問などは難しい)・(質問に答えるのは難しい)
- ディズニーランドに行くことができた
16歳からは家から比較的近くにある養護学校に通いました。
養護学校では発達障害以外の、身体障害の方・脳性麻痺などの重症心身障害の方・知的障害の方などさまざまな障がいを持つ方が通っており、
兄はいままで発達障害の方か、正常発達の方としか出会っていなかったので、今までと接し方が違ったようです。
例えば、
話すことが難しかったり・歩くことが難しい方など、自分よりもできることが少ない方に対していろいろな場面で助けようとしたり、
絵本が好きな子に本の読み聞かせをするなど、相手を思って行動する場面が増えたそうです。
養護学校に入ってから、相手に意識が向くようになった気がすると母は話していました。
他には、
- シール貼りや箱組み立てなどの作業ができるようになった
- 簡単な質問に答えられるようになった
- 言葉は単文ではあるが、簡単なコミュニケーションがとれるようになってきた
養護学校に通う間にも成長がみられました。
19歳〜現在:生活介護の利用と現在の成長
養護学校を卒業した後は、日中は生活介護を利用するようになりました。
兄が利用しているのは、B型就労移行支援事業所のように、箱を組み立てたり、シールを貼ったりなどさまざまな作業を行うことを中心とした生活介護事業所です。
B型就労移行支援はあくまで、お仕事をするという要素が強いので、時間の通りに動かなければならないし、
工賃が発生するので社会人としてのルールなども求められる部分があるのですが、
兄はそこまできっちり行うことが能力的に難しい、通常の生活介護でよく行われる集団でリクリエーションをしたりするのも苦手なので、
母は作業を行うことが中心で、本当に少ないけれど働いたことで賃金をもらう経験ができる、なおかつ適度に自由な行動が許される生活介護に決めたそうです。
兄は現在も、楽しく通っています!(^^)!
- 平日、毎日決まった時間に通って働くことができている
- 1人でバスや電車にのって出かけることができるようになった
- 生活介護に通う他の利用者に対して、本の読み聞かせをするなど役割ができるようになった
- 自分からこうしたいと希望を伝えたり、解決策を考えることができるようになった
- 複文で話せることが増えた
現在までの兄の成長は、上記の通りです。
最近の発達検査では、言語や社会の力については小学1年生ほどの力で、認知は小学校高学年ほどの力という結果でした。
コミュニケーションにおいて、今も少しずつ成長がみられています。


簡単ではありますが、兄の経歴はこのような感じです。
少し様子がおかしいな?と母が感じたのが兄が2歳半の時でした。
言葉の遅れが1番のきっかけだったそうです。
診断結果は自閉症+知的障害ということでした。
診断にはありませんでしたが、ADHDの多動傾向が強く、良く走り回り飛び跳ねる男の子でした。
母のすごいな~と思うところは、診断に驚き、ショックを受けつつも、少しずつ障害を受け入れて、本を読んで自閉症について勉強し、
早い段階で本を読んだり、療育に通う決断をしたことです。
ここで母がショックをうけたまま障害を受け入れられず、療育にかかるまでに時間がかかっていたら、今と違う兄になっていたのかなと思います。
では次に、
- 兄が受けていた療育はどんなものか
- 効果があったか
- 発達分野の作業療法士からみて兄の発達に良い影響があった理由を考える
の順番でお話ししていきますね。
自閉症の兄に合っていた療育とは?
では兄が利用していた療育・知育について、お話ししていきます。
兄が受けていた療育2つ
まず兄は、3歳から児童発達支援センターへ通い、
- TEACCHプログラム(ティーチプログラム)
- 音楽療法
を受けていました。
母は中でもTEACCHプログラムは、兄の言葉の発達にすごく影響があったんだと思う!と話しています。
TEACCHプログラム(ティーチプログラム)とは?
自閉症の特有のニーズ5つについてお話ししました。
次に、TEACCHプログラムとはなにか、簡単にお話ししていきますね。
TEACCHプログラム(ティーチプログラム)ってなに?
TEACCHプログラムとは、自閉症の人たちが持つ特有のニーズに合わせて作られた教育支援プログラムです。
自閉症の人たちが学びやすいように、視覚的な情報を活用していたり、日常生活のルールや手順をわかりやすく整理して示していることが特徴となっています。
目的は、高度なコミュニケーションがとれるようにすることではなく、簡単な意思疎通ができることを目的としているので、幼い子どもでも取り組みやすいプログラムになっています。
TEACCHプログラムの具体的な方法
説明を聞いても、ふわっとしていてわかりにくいですよね💦
具体的にどんなことをしているのか5つにまとめて説明していきますね♪
①視覚的な手がかりを使う
絵や写真、スケジュール表を使って、何をするかが一目でわかるようにします。
例えば、学校のスケジュールを絵で見せることで、次に何をするかがわかりやすくなるんです。


②はっきりとした環境づくり
部屋や机をきれいに分けて、『ここで勉強する』・『ここで休む』と場所ごとに役割をはっきりさせます。
これによって、自閉症の人が今何をするべきかを理解しやすくなるんですよ~♪


③ルーチンの確保
毎日の予定を決まった順番で行うことで、安心して過ごせます。
もし変化があるなら、事前に伝えることで不安が少なくなりますよ~♪
④簡単な指示やタスク
課題や仕事を小さく分けて、1つずつ進められるようにします。
これにより、集中しやすくなり、達成感を感じられます。
⑤感覚のサポート
音や光が苦手な場合、イヤーマフを使ったり、静かな場所で作業するようにします。


このように、TEACCHプログラムは、それぞれの自閉症の人が持つ特別なニーズに合わせてサポートを工夫して、
自分のペースで成長できるように手助けするものなんです。
これによって、自閉症の人が自立した生活を目指しやすくなります。
兄がTEACCHプログラムをした効果は?
ティーチプログラムを始めた兄は、TEACCHプログラムの中の、視覚的な手がかりを使うと、はっきりとした環境づくり、ルーチンの確保から主にやっていきました。
外出するときにどこに行くのかわからず不安からパニックになって嘔吐していた兄でしたが、
前日に行く場所の写真や、パンフレットをみせることで、パニックでの嘔吐がなくなりました。
しかし、行ったことがない場所は、あまり効果はありませんでした。
さらに、1人で集中して本を読んだり、プラレールを作ったりして落ち着いて過ごす部屋(妹と兼用)を作り、寝る場所、ごはんを食べる場所を固定すると、支度がスムーズに。
ご飯を食べる順番も決めていました(笑)
ルーチンは成長していくにつれてはっきりしていったため、それに合わせていく形でした。
また、母はTEACCHプログラムの絵カードを使った練習で言葉を覚えることができたと話しています。
実際には、同時に児童発達センターで、言葉の発達を専門とする言語聴覚士さんの支援も受けていたそうなので、その影響も大きかったと思います。
兄の場合は、この2つがうまく合わさったことで、少しずつ言葉が増えていったのだと感じています。
TEACCHプログラムは、本人が生活しやすくなるのはもちろん、周りの人も生活しやすくなったり、本人に接しやすくなったりもなるので本当に良いプログラムだと思います。
自閉症の度合いや、知的障害の有無などで、もう少し高度なプログラムがあったり、リハビリなども有効だと思うので、まずは医療・福祉機関で相談することをオススメします♪
音楽療法とは?
もう1つ兄が実施していた療育である、音楽療法についてお話ししていきます。
まず、音楽療法とはなにか?簡単に説明しますね。
音楽療法ってなに?
音楽療法は、音楽を使って心や体の調子を良くするための治療方法です。
音楽を聞いたり、歌ったり、楽器を演奏したりすることで、
リラックスしたり、ストレスを減らしたり、気持ちを明るくすることができます。
例えば、病院で入院している人が音楽を聴いて元気を出したり、学校で音楽を使ってみんなで楽しく活動して、友達ともっと仲良くなるために使ったりします。
音楽は気持ちを伝えたり、心を落ち着かせたりする力があるので、専門の先生がその力を使って、より健康的になるよう手伝ってくれるんです。
音楽療法は、自閉症の人や高齢者、心に不安を抱えている人など、いろいろな人に役立つ方法です。
自閉症に対する音楽療法の具体的な方法は?
自閉症の人に対する音楽療法では、音楽を使ってコミュニケーションや社会的なスキルを高めるサポートをしています。
では、自閉症の人に対してどのように音楽療法を行っているのかを簡単にお話ししていきますね。
①音楽に合わせて感覚を使った活動
音楽に合わせて手をたたいたり、布にくるまって揺れたり、太鼓を叩いて振動を感じたり、リズムに合わせて動くことで、体の動きを感じながら協調性を学んだり、感覚刺激を身体で感じることができます。
そうすることで、安心感を得られたり、運動発達に良い影響があるんです。


②歌を歌う
簡単な歌を一緒に歌うことで、言葉の練習をしたり、感情を表現する練習をします。
歌うことで自然に言葉や表現を覚えていきます。
③楽器の演奏
簡単な楽器を使って音を出すことで、自分の意思で音を作り出す楽しさを体験します。
これにより、自信を持って自分を表現できるようになります。
④音楽を聴く
リラックスできる音楽を聴いて、心を落ち着けたり、不安を和らげる時間を過ごします。
音楽療法は、楽しみながら行うので、自閉症の人が無理なく参加しやすく、少しずつコミュニケーション能力や集中力を高める助けになるんですよ。
兄が音楽療法をした効果は?
兄はもともと音楽が好きだったので、音楽療法はぴったりでした。
音楽療法を通して楽器の音も好きになり、お祭りなどの苦手な人混みでも、太鼓の音や盆踊りの音楽などがあれば楽しくいられるようになりました。
好きな曲もできました。それは、Disneyソングやピアノの演奏曲。
今でも朝に聴いて、リラックスしているようです(^-^)
兄は現在31歳ですが、今でも音楽が好きで、リラックスしたいときはDisneyソングやクラシックを聴いて、
テンションを上げたいときは、ジャンボリミッキーなどの楽しいDisneyソングや、お母さんと一緒の音楽を聞いたり、ゲームの音楽を聴いて過ごすなど、
自分でコントロールして音楽を楽しむことができています(*^^*)
自分の興味のあるものだけでなく、最近は私や母が聴く曲も一緒に聴けるようになりました。(凄い!)
中でも『sekainoowari』さんが好きなようで、コンサートも行ってみたいと話していました。
31歳になっても成長がとまらない兄に母といつも感動しています( ;∀;)
作業療法士からみた兄の成長の理由とは
作業療法士として兄が成長した理由には大きく分けて3つが影響しているのではないかと思ったので、お話ししてきます♪
早期の気づきと療育の開始
まず1つ目は、母が兄の言葉の遅れに対して、「少しおかしい・・・」という違和感を大切にして、すぐに専門機関に相談したことが大きかったと思います。
当時は発達障害の情報が少ない時代でしたが、「今できることをやってみよう」とすぐに行動に移したことで、成長をサポートするスタートを早く切ることができました。
そのおかげで早期から兄はいろいろな体験ができ、専門的に発達の成長を促すことができたのではないかと思います。
好きなことを活かせる環境づくり
2つ目は、兄の『好き』を周りが理解し、好きなこと・得意なことを伸ばす環境・安心できる居場所を作ることができたことです。
兄にとって音楽は大好きなものでした。
音楽療法を通して、楽しいことを『安心できる場所』として取り入れられたことで、苦手な状況(お祭りの人混みなど)でも、音楽があれば楽しめるようになっていきました。
また、体操教室や保育園での集団生活など、兄の特性を理解してくれる大人や友達がいたことで、『できないことを責められない環境』で挑戦する経験を積めたのは大きかったと思います。
家族の関わりと小さなチャレンジの積み重ね
3つ目は、『できないからやらない』ではなく、『どうすればできるか』を一緒に考えることができたこと。
作業療法士として見ても、家族の関わり方はとても大切です。
母はもちろん、私も妹として一緒に過ごす中で、
兄が『安心できる』・『チャレンジできる』環境を作ることができていたと思います。
「できないからやらせない」ではなく、「どうしたらできるかを一緒に考える」姿勢が、兄にとって1歩ずつ成長する原動力になったと感じています。
おわりに
兄の幼少期からの療育は、大人になってからの趣味や安心できる方法として今も活かされています。
音楽も視覚的支援も、本人の安心につながり、周囲も関わりやすくなりました。
療育は1人ひとりに合う形が違うからこそ、この記事が「どんな環境や支援が合うのか」を探してみるヒントになれば嬉しいです。
兄のこれからの成長も、家族みんなで見守っていきます(^-^)
ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪
まとめ
今日のまとめ
兄が受けていた療育は2つあります。
1つ目はTEACCHプログラム、2つ目は音楽療法です。
TEACCHプログラムとは?
✅自閉症の人たちが学びやすいとうに、視覚的な情報を活用していたり、日常生活のルールや手順をわかりやすく整理して示していることが特徴。
✅目的は、高度なコミュニケーションがとれるようにすることではなく、簡単な意思疎通ができることを目的としているので、幼い子どもでも取り組みやすいプログラムになっている。
兄がTEACCHプログラムをした効果は?
✅外出するときにパニックになっていた兄だったが、前日に行く場所の写真やパンフレットをみせると、パニックを起こさなくなった。
✅1人で集中して本を読んだり、プラレールを作ったりして落ち着いて過ごせる部屋(妹と兼用)を作り、寝る場所、ごはんを食べる場所を固定すると、支度がスムーズになった。
音楽療法とは?
✅音楽療法は、音楽を使って心や体の調子を良くするための治療方法。
✅音楽を聞いたり、歌ったり、楽器を演奏したりすることで、リラックスしたり、ストレスを減らしたり、気持ちを明るくすることができる。
✅音楽療法は、自閉症の人や高齢者、心に不安を抱えている人など、いろいろな人に役立つ方法。
兄が音楽療法をした効果は?
✅兄はとにかく音楽が大好きになって、お祭りなどの苦手な人混みでも、太鼓の音や盆踊りなどの音楽があれば楽しくいられるようになった。
✅モーツァルトの曲でリラックスができるようになった
✅30歳の今でも、リラックスしたいときはDisneyソングやクラシックを聴き、テンションを上げたい時はジャンボリミッキーなどの楽しいDisneyソングを聴くなど、
自分でコントロールして楽しむことができている。
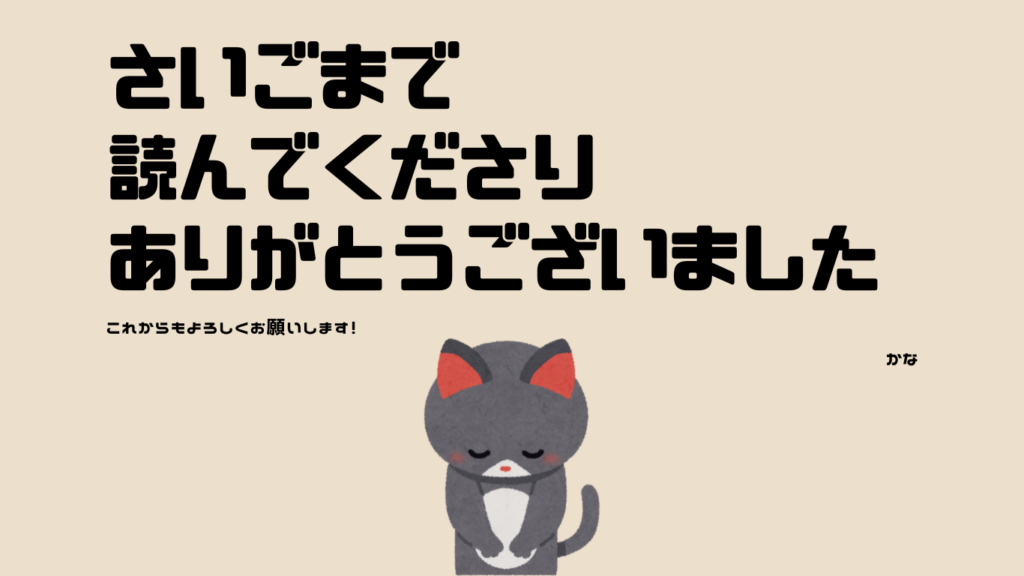
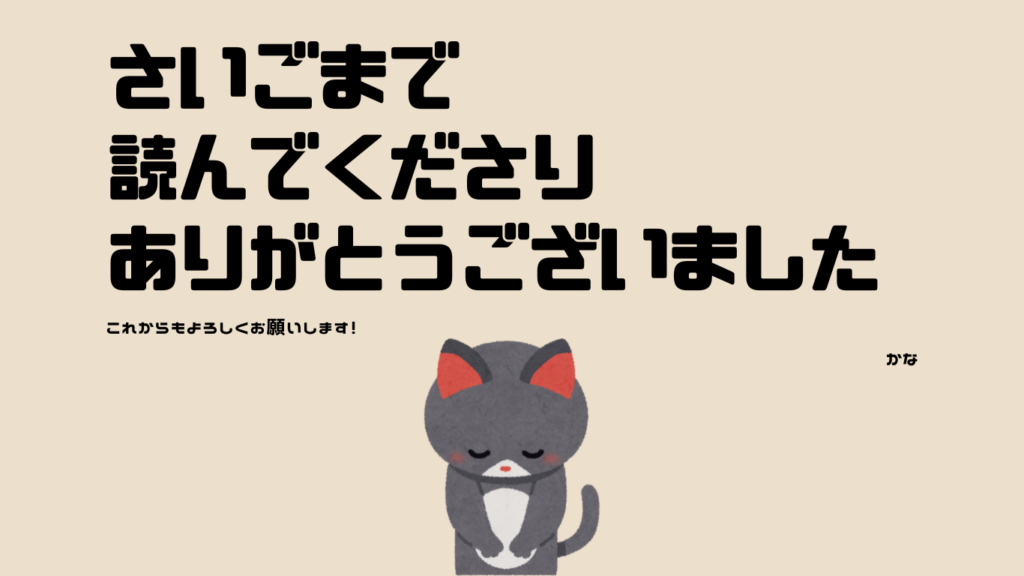

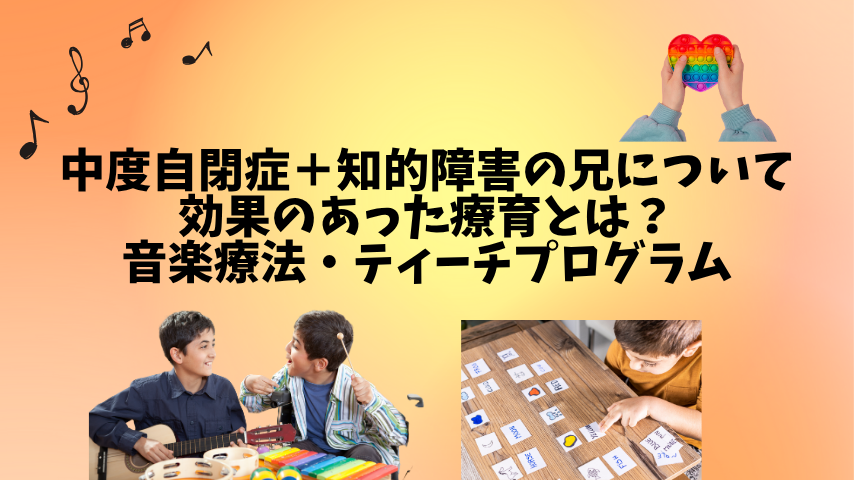
コメント